お知らせ
「長時間かけて書いたコメントが送信できなかった」等の送信エラーのご報告をいただいております。
こちらは一定時間が経過した段階で、タイムアウトと判断している為です。
掲示板のセキュリティ上、どうしてもタイムアウト時間を設定する必要がございます。
つきましては、メモ帳などで下書きいただく等でご対応いただければ幸いです。
今後とも当掲示板をよろしくお願いいたします。
 メイン メイン [00-02]オーディオ全般 [00-02]オーディオ全般
 リファレンス・ディスク(JAZZ編) リファレンス・ディスク(JAZZ編) | 投稿するにはまず登録を |
| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| 管理人K | 投稿日時: 2008/3/22 4:23 |
管理人   登録日: 2007/12/10 居住地: 投稿: 1935 |
リファレンス・ディスク(JAZZ編) リファレンス・ディスクのご紹介。
最後はJAZZ編です。 JAZZに関して私は、50〜60年代のハードバップやモード、フリーJAZZをアナログレコードで聴く事が多いのですが、アナログプレーヤーをお持ちでない若い方のためにも、今回のリファレンス・ディスクでは新しい録音のCD盤をご紹介させて頂きます。 Lee Ritenour 「Wes Bound」  リー・リトナーのウエス・モンゴメリー作品を中心にしたセミ・アコースティックギターによる演奏です。 高音質録音の多いGRPレーベルから発売されているディスクで、今回紹介するものはCDカッティング時にセシウムクロックを使用した限定盤です。 よく使うトラックは3の「4 on 6」で、セミアコの質感や時折入るホーンセクションの質感と位置関係、ドラムスの切れ味や演奏の疾走感などが非常に参考になります。 オーディオシステムの低域の制動が効かず、低域方向がノイズや歪みなどで膨らんでしまっていると、セミアコの音が膨張してディティールが全く出なくなってしまい、ボワボワ、モコモコした切れの悪いギターになってしまいます。 また、ドラムスの切れ味もなくなり、演奏の疾走感がなくなり、のろまで鈍重な演奏に感じられるようになってしまいます。 位相特性が悪いシステムですと、後ろにいるべきホーンセクションが前に張り出してしまい、ノイズや付帯音、歪みが多いとホーンセクションがギラギラした音色で非常に耳障りなやかましい音色に成り果ててしまいます。 Kenny Barron 「Wanton Spirit」 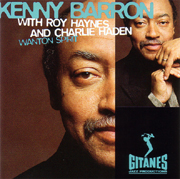 ケニー・バロン(ピアノ)、チャーリー・へイデン(ベース)、ロイ・へインズ(ドラムス)のピアノトリオによる、スリリングな演奏が楽しめる94年発売のディスクです。 最近はカッティング時にセシウムクロックを使用したリマスター盤なども販売されているようです。 ライナーノーツに録音時の写真が載っていますが、ピアノとドラムスはパテーションで仕切り、ベースは別ブースで演奏するという相互の音の干渉を防いで、極力それぞれの楽器の音だけを録音した後にミックスするという手法が取られているようです。 ピアノの艶などの質感、ベースの深い沈み込み、ドラムスの切れなどが非常に参考になるディスクです。 よく聴くトラックは1、3で、特に3における冒頭の1分半に及ぶチャーリー・ヘイデンの深く沈み込むベースソロが聴き物で、低域方向のノイズのなさや最低域の再現性などが、ベースのディテールや沈み込みに大きく影響します。 また、ベースソロの後にピアノと共にスリリングに登場するロイ・へインズのシンバルワークの質感再現も大切な要素になります。 ノイズや付帯音にまみれたシステムでは、リアルなシンバルの質感もピアノの質感も再現出来ません。 Lee Konitz 「Rhapsody」 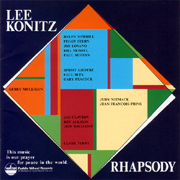 クールJAZZの巨匠、アルトサックスのリー・コニッツの様々な楽器、アーチストとの知的なインタープレイが楽しめる作品です。 ヘレン・メリルなどヴォーカリストのインタープレイも収録されています。 録音は日本のエンジニアが担当されているようですが、どの楽器や声も非常にナチュラル且つエネルギー感に富んだ音色、質感で録らえられていて素晴らしいものがあります。 どのトラックも生楽器や生声そのもの質感が味わえますので、いかにその自然な質感が再現出来るかがポイントになるディスクです。 付帯音や音色的な癖が強いシステムやケーブル、アクセサリーではこの自然な質感が台無しになってしまいます。 よく聴くトラックはジェイ・クレイトンのヴォイスインプロビゼーションが楽しめる3で、前衛的なヴォーカルとコニッツの軟らかいサックスとの対比が素晴らしいのですが、ノイズや付帯音、歪みの多いシステムではヴォーカルもサックスも質感が出せずにインタープレイの妙も再現出来なくなってしまうでしょう。 Joe Henderson 「Double Rainbow」 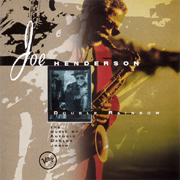 ジョー・ヘンダーソンの晩年の作品で、ボサノバのスタンダードを前半がブラジルのアーチストと、後半がハービー・ハンコック(ピアノ)、クリスチャン・マクブライド(ベース)、ジャック・ディジョネット(ドラムス)と競演しています。 お薦めは後半の凄腕アーチストとのスリリングな演奏ですが、音質的には全編に渡ってジョー・ヘンダーソンの軟らかく質感の高いサックスの音色が楽しめます。 バックの演奏の音色や質感が前半では軟らかめ、後半では幾分硬質に変化するのが聴き取れるかもポイントになります。 質感が悪いシステムやケーブル、アクセサリーではこの演奏の硬質感の違いも出せないでしょうし、サックスの音色や質感もがさつなものになってしまうでしょう。 Ray Bryant meets Ray Brown 「Double RB」 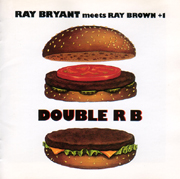 「RB」はレイ・ブライアント(ピアノ)とレイ・ブラウン(ベース)の二人の巨匠のイニシャルから取った洒落たタイトルです。 若手のルイス・ナッシュをドラムスに迎えたピアノ・トリオの傑作アルバムです。 瑞々しく艶やかなレイ・ブライアントのピアノ、強靭に引き締まり深く沈み込むレイ・ブラウンのベース、切れの良いルイス・ナッシュのドラムスが全編で楽しめます。 よく聴くトラックは最終11のチャーリー・ヘイデン作の「ファースト・ソング」でレイ・ブラウンのアルコ弾き(弓弾き)から始まります。このベースのアルコ弾きによる胴鳴りの豊潤さと、ピッチカートに切り替わった際の切れ味の良さの違いが、いかに克明に再現出来るかで低域の再現性が測れると思います。 ノイズや付帯音が多く濁ったシステムやケーブル、アクセサリーではこのレイ・ブラウンのベースのニュアンスの違いが出難く、演奏の凄みが伝わりませんし、レイ・ブライアントのピアノの瑞々しさも台無しになってしまうでしょう。 Gary Peacock Ralph Towner 「Oracle」 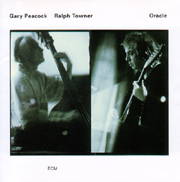 ゲーリー・ピーコック(ベース)とラルフ・タウナー(ギター)による高度でスリリングなインタープレイが楽しめるアルバムです。 発売はECMでご存知の通り北欧ノルウェーの首都オスロのレインボウスタジオにおける録音でプロデューサーはマンフレッド・アイヒャーです。 他のECM盤同様、この盤も独自の透明で温度感の低い空間を感じる録音になっています。 非常にリアルな音色と質感でベースとギター音像を録られており、各音像共に適正な大きさで、ゲーリー・ピーコックの息使いまで生々しく収録されており、正に目前で二人が演奏をしているような錯覚に陥ります。 ノイズや付帯音、歪みがあると、ピーコックの強靭で硬質なベースの質感や、タウナーの様々な種類のギターの弾き分けも克明に再現出来なくなって生々しさも半減してしまいます。 Olga Konkova 「Going with the flow」 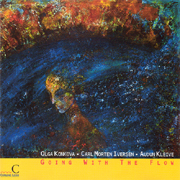 ロシア出身の女流ピアニスト、オルガ・コンコワのピアノトリオアルバムです。 録音は先程の「オラクル」と同じ、オスロのレインボウスタジオとなっています。 発売はECMではありませんが、不思議な事に先程のオラクルや他のECM盤同様の透明で温度感の低い空間を感じる録音になっています。 透明でクリア且つ重厚なピアノの響きと深いベースと歯切れの良いドラムスのサウンドが特徴になります。 ECMにおけるピアノ録音よりも、エネルギー感と厚みが優れているように感じます。 前記のオラクル同様、透明な空間表現や優れた楽器の質感や低域方向の深い再現性はノイズや付帯音、歪みがない事が求められます。 Ellis&Branford Marsalis 「Loved ones」 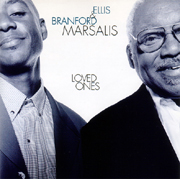 エリス・マルサリス(ピアノ)とブランフォード・マルサリス(サックス)の親子のデュオによるスタンダード集です。 特にピアノの音質が素晴らしく、あらゆるJAZZピアノ録音において最高峰と言える艶、質感、エネルギー、周波数レンジ、ダイナミックレンジなど全ての項目がパーフェクトに録らえられています。 サックスもかなり大き目ではありますが、質感高くエネルギー感豊かに収録されており、親子による絶妙な駆け引きが堪能出来ます。 但し、このエネルギー豊かなピアノとサックスの音色や質感もノイズや付帯音、歪みの多いシステムやケーブル、アクセサリーでは全て台無しにされてしまいます。 ピアノも汚れてサックスは聴くに絶えない刺激的な音色と質感に変わり果ててしまうでしょう。 Hugh Masekela 「Hope」 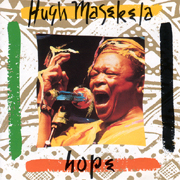 このアルバムは知り合いの輸入代理店の方からラスべガスのオーディオショー土産に戴いて知ったもので、演奏は南アフリカのフリューゲルホーン奏者ヒュー・マセケラです。 アフロミュージック的な独特のJAZZで、非常に熱い魂を感じさせる演奏です。 最近は米国アナログプロダクションから45回転重量盤のアナログレコードも発売されていて、これがまた圧倒的な高音質となっていますので、アナログをやられている方は売り切れる前に今すぐ入手される事をお薦め致します。 「Hope」45回転重量盤レコードの入手はこちらでどうぞ http://store.acousticsounds.com/browse_detail.cfm?Title_ID=41717 特に最終トラック12の「Stimela(The Coal Train)」の演奏は圧巻で、マセケラのフリューゲルホーン&トランペットと黒人ヴォーカリストの圧倒的にパワフルなシャウトによる凄まじい熱演が恐ろしくリアルな空間で再現され、完璧にKOされてしまいます。 このリアルでエネルギッシュで濃厚なライヴ空間を再現するには システムのエネルギー感やダイナミックレンジが求められますが、 それ以上にそのエネルギーやダイナミックレンジをスポイルしない ケーブルやアクセサリーの使用が必須です。 またヴォーカルなども余りに強烈なエネルギーのため、ノイズや付帯音、歪みがあると子音などが煩くて聴けなくなってしまう恐れもあります。 以上、JAZZ演奏におけるリファレンス・ディスクをご紹介させて頂きました。 JAZZは何でもかんでもパワフルで押し出しが良ければ良いというものではありません。 いかに楽器の音色や質感をリアルに録らえて、高S/N比で演奏の間なども克明に録られられなければ、本当の演奏の凄みなどは感じ取れないと個人的には思います。 ピアノの種類による音色差や、ピアニストのタッチの違いによるピアノの音色差なども再現されなければいけないと思います。 |
| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 投稿するにはまず登録を | |
